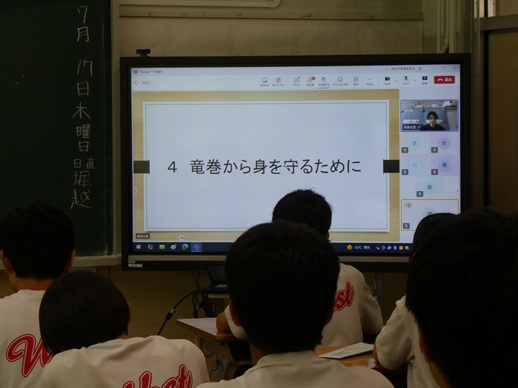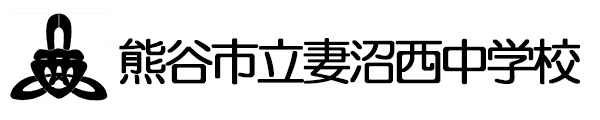9月1日避難訓練
9月1日避難訓練
校長 清水利浩
本日の避難訓練は、竜巻の発生に対する訓練です。皆さんは、廊下に出て、頭を守る姿勢をとり、身を守るなど、訓練にしっかりと臨むことができました。なぜ、この時期に避難訓練を行うのか、2つの点についてお話します。
まず1つ目。1923年9月1日正午近く、関東大震災が起きました。今から102年前の今日のことです。関東南部を震源とする地震で、熊谷は震度6でした。多くの家屋が被害を受けました。また、今日の全校集会でお話した2年前の能登半島地震の記憶は皆さんもあると思います。
今後、南海トラフに関わる巨大地震をはじめ、いつこのような大地震が発生するかわかりません。自分は絶対大丈夫ということでもありません。
2つ目は、竜巻についてです。今から12年前の平成25年(2013)9月16日、台風18号における竜巻被害が熊谷市を中心に数か所で発生しました。深夜1時30分から2時ごろ、いくつもの竜巻が発生し、妻沼地区では、長井小学校から妻沼東中学校あたり、幅200~300m、長さ8kmの範囲で、屋根瓦が飛び、ガラスが割れる。軽自動車が横転する等。熊谷市全域では住宅全壊10棟、1021棟が被害を受けました。
これも9月の出来事です。
さて、災害が発生したときに皆さんはどう動きますか。自助・共助・公助という言葉があります。
まずは、自分の身をしっかりと守ってください。これを自助といいます。
そして、周りの方々の避難に協力してください。共助といいます。
そして、本来、市役所の方々が行うのかもしれない避難所の開設などの公の仕事にも協力をしてください。これを公助といいます。
当然、中学生として、できることできないことがあります。自助、共助、公助。 特に共助と公助の場面で、しっかり考え、行動に移してください。この場面でも、「正しい判断力とたくましい実践力」を発揮しなければなりません。ぜひ、今回の避難訓練を受けて、おうちでも自然災害について、その時の避難について、話題にしてください。
よろしくお願いします。