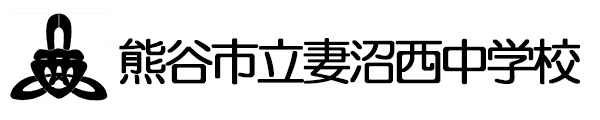令和7年度後期始業式式辞
3年生が調べた「戦争」に関するレポートについて
校長 清水 利浩
戦後80年といわれます。1945年に第2次世界大戦がおわり、今年2025年で80年がたちます。3年生の皆さんが、夏休み中の社会科の課題として作成した、戦争に関するレポートを拝見しました。さすが3年生。素晴らしいものです。2人の感想を紹介します。
「このレポートが出るまで、終戦の直前にここまで大きな熊谷空襲があったことを知りませんでした。戦争が終わることが分かっていた中で、一晩のうちに多くの命が奪われてしまったこと、町だけでなく、人々の心まで傷つけられてしまったこと、とても悲しい事実です。今、私たちは、学校に通うことができ、家族も友達もいます。おいしいご飯が食べられます。これらのことは、決して当たり前のことではなくて、平和に暮らしていることがどれだけ幸せなのか気づかされました。これから二度と戦争を起こさず、平和に暮らしていくには、地域の歴史を詳しく知り、戦争の恐ろしさや命の重みなどを多くの人に伝えていくことが重要であることもわかりました。少しでも自分が社会で役に立てるようにボランティアや募金といった平和のためにできる行動を心掛けていきたいと思います。」
「おばあちゃんが昔、体験した人の話を教えてくれました。熊谷空襲の時、星川に逃げ込んだ人は川が小さすぎるのと人が逃げ込みすぎて水が熱く大勢の人がなくなりました。しかし、荒川に逃げた人はほとんどの人が助かったと。
熊谷市には、戦闘機を製造していた中島飛行場の下請け工場がたくさん存在していったため、軍需産業の拠点とみなされました。中島飛行機の工場に物資や人を運ぶための刀水橋を破壊したかったいろいろ教えてもらいました。これからは、戦争について、年配の方などとお話しして、次の世代に戦争の残酷さなどを伝えていきたいと思います。」
校長先生からは、かつてあった「妻沼駅」のことをお話しします。
東武熊谷線は、群馬県にあった中島飛行機工場で働く工員や資材を輸送する必要性から、戦争中、軍の命令で建設されました。工事は2期に分けて始まりました。第1期は、熊谷―妻沼間⑴。軍の命令で急ピッチに進められ、熊谷駅を出て、右に曲がってからは、ほぼ一直線に線路が引かれました。戦争中で物資が少ないため、線路などは、東武日光線として複線で開業していた線路の片側を撤去して、熊谷線に持ってきたようです。高崎線沿線などに住む工員たちは、列車で熊谷駅から妻沼駅まで来た後、バスに乗り換え、刀水橋で利根川を渡り、工場へ通勤しました⑵。当時は、蒸気機関車が、多い時は五両もの客車を引いて妻沼駅へやってきました。妻沼駅前には、太田工場と小泉工場行きに分かれて、バス7,8台が待ち、工員たちは長い列をつくってバスに乗り込んでいきました。工員の通勤の足を確保するため、飛行機生産のピーク時には、三交代の工員を送迎するために、昼夜、ピストン運行されました。妻沼駅は、乗り換えの駅として大変にぎわっていたようです。駅前には、売店。その奥に東武バスの大きな車庫があり、運送会社(丸通)があり、トラックが群馬まで資材を運んでいました。第2期工事は、妻沼から利根川を渡り、西小泉駅に接続する計画でした。しかし、完成前に終戦となります。その後、熊谷線は利根川を渡ることなく、1983(昭和58)年5月31日、廃止となりました。妻沼駅の東側(今のカスミあたり)には、利根川鉄橋工事の資材がたくさん置かれ、近くの子どもたちは、その資材の山で登ったり降りたりして遊んでいたそうです。この資材は、のちに赤城山東側の地上ケーブルに利用されたといいます。地上ケーブルは、赤城山大沼の東側から小沼、桐生方面に伸びていました。その後、廃止して、今はありません。
妻沼の中央公民館にあるクリーム色の妻沼線の車両は、かつて賑わいをみせた妻沼駅と、完成することなく、走ることのなかった利根川を渡る第2期工事区間の方角を向いています。
⑴工事の許可がおりたのは1942年6月。翌年11月に工事を開始し、1944年12月に完成。わずか1年足らずで完成させたスピード工事でした。
⑵中島飛行機工場では、約8000機もの軍用機の生産を行っていました。1944(昭和19)年、この中島飛行機工場で働いていた人は、太田工場で67000人、小泉工場で88000人だったといわれています。
○作成にあたり、青木久夫先生に、いろいろなお話や参考となる資料を紹介していただきました。
<参考>「なつかしの妻沼線40年の歩みー写真にみる東武熊谷線」平成4年3月熊谷市立図書館